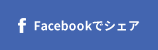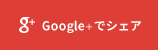まさかなぁと思って相談してみたら、まさかの過払い金120万円ありました。 全ての払いが終わっていた…
過払い金請求と立替金が相殺適状となるケースについて
9262view
2018.07.05
カテゴリー:
相殺適状とは?

相殺とは?
過払い金請求とショッピング立替金が相殺適状となるケースと、そうでないケースとがあります。ここでいう相殺とは、債務のある者が、債権を有する者に対して同じような債権を持っているとき、自分が果たすべき債務と債権とをそれぞれ対当に消滅させることをいいます。
相殺自体は、人間社会において古くから認められている制度ですが、裁判が行なわれない限り認められないという場合もあれば、相殺できるような状態にさえなっていれば、相殺されたものとみなす法例もあり、さまざまです。
日本の民法(506条1項)では、相殺契約があるとき、債務者から債権者(あるいはその逆)への一方的な意思表示があるとき、相殺が成立すると定められています。相殺する方の債権のことを自働債権、逆に相殺される方の債権を受働債権と呼んでいます。
相殺適状とは?
相殺が可能であるための要件のことを相殺適状といいます。当事者間に、同じような種類の債権をそれぞれ負っていて、互いの双債権がどちらも弁済期、すなわち支払うべき時期にあるときが、これに当たります。
ただし、相殺したいと考える人の自働債権が弁済期にあるとき、仮に相手方が有する受働債権が同じように弁済期になくても、受働債権に掛かる期限の利益を放棄すれば、すぐに相殺することもできます。
相殺ができない場合について

相殺が認められないケース
上記のような相殺適状を満たしていても、次のようなケースでは相殺することができません。たとえば、債権の特徴からいって債務の実際の履行が欠かせず、相殺してしまうと債権の本来の目的が達されないときです。また、当事者どうしで相殺しないことを特約した場合も、相殺することはできません。
ただし、この特約は常に有効なわけではありません。特約があることを知らずに債権を譲り受けたときは、相殺することが可能です。そのほか、債務が手続きのもとで得られた場合など、法律で相殺が禁止されているケースもあります。
時効で消滅した過払い金返還請求権の取り扱い

時効で消滅した債権は、遡って相殺が可能
民法508条では、次のように記されています。「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。」
つまり、時効が成立したことで消滅してしまった債権があったとしても、それが消滅する以前に相殺適状を満たしていれば、相殺することが可能であるというわけです。相殺とは本来、当事者の意思表示があることではじめて成立するものです。
そのため、かつては相殺適状になっていたとしても、どちらかが意思表示しないうちに時効を迎えれば、債権が消滅してしまい、相殺適状は失われてしまうはずです。
ところが、時効が成立する以前に相殺適状が満たされていたとするなら、当事者それぞれの債権が相殺によって清算されたことを期待するのは自然なことです(仮にどちらからも意思表示がなかったとしても)。そのため、お互いに何の申し合わせがなくても、過去に遡って相殺されたことが追認される場合があるというわけです。
時効で消滅した過払い金とショッピング立替金の相殺
この法律を過払い金請求とショッピング立替金に当てはめて考えると、次のようになります。貸金業者を利用した債務者が、貸金業者に対して過払い金があるとします。一方でショッピング立替金も残っているため、双方の債権どうしを相殺したいと考えました。ところが、過払い金の返還請求権は、時効成立にともない消滅してしまっています。
時効が成立してしまっている時点で借入金の残金を相殺したいと主張しても、貸金業者側は、当然のことながら時効消滅を理由に拒否してきます。
本来であれば、意思表示がないまま時効を迎えた時点で、相殺をあきらめなければいけないところですが、民法508条により、過去に相殺適状が満たされた時点で、相殺が行なわれたことが認められ、借入金の債務が減る、ないしは消滅するというわけです。
時効消滅した過払い金請求と、借入金残金債務やショッピング立替金とを相殺するのは、かなり難しくなったというのが現状です。過払い金請求をする際には、どの時点で相殺適状が生じたか、これまで以上に精査が必要となりそうです。
相殺適状に関する最高裁による重要な判例

事案の大枠と問題の所在
過払い金の充当に関して、たいへん興味深い判決が平成25年に最高裁判所で下されました。そもそもの事案はおおよそ次の通りです。貸金業者を利用したAの貸金業者Bに対する本件過払い金返還請求権は、平成18年に時効成立により消滅しました。
Aは、Bに対する貸付金残債務を負っていますが、平成22年7月1日の返済期日までに支払いをしなかったため、期限の利益を失っています。平成22年8月、AはBに対して、自らが有していた本件過払金返還請求権を自働債権とし、Bが有する貸付金残債権を受働債権として、相殺したいとの意思表示を行ないました。
平成22年9月、BはAに対して、本件過払金返還請求権が時効成立のため、すでに消滅していることを主張します。Aは、平成22年11月までに相殺適状が満たされていたため、その時点で貸付金残債権の残元利金は支払済みであると主張します。
ここで問題とされたのは次の2点です。まず、自働債権と受働債権とが相殺適状を満たしたのはいつだったのかという点です。受働債権に掛かる期限の利益を放棄することができるのか、また、期限の利益を放棄したことで、弁済期が到来したのかどうかが問われます。
もうひとつの問題は、消滅した債権を自働債権として相殺を実現するためには、自働債権が時効成立を迎える以前に、受働債権と相殺適状になくてはならないか、ということです。
平成23年、札幌高裁では、相殺を認める判決が下されました。貸付金残債権は貸付されたときに発生しているため、Aは期限の利益を放棄しさえすれば、過払金返還請求権と相殺可能になるため、平成15年にABの間で債権と債務がそれぞれ対立する関係が成立し、双方の債権は相殺適状になったというのです。
さらに、過払金返還請求権と貸付金残債権とはまったく対当に相殺できるため、Aの貸付金債権は消滅しているとされました。
最高裁では相殺を認めない判決が下される
Bは、札幌高裁での判決不服とし、上告受理申立てを行ったところ、平成25年、最高裁で破棄・差し戻しとなってしまいます。
判決要旨は次のようなものでした。弁済期にある自働債権と受働債権とが相殺適状にあるためには、受働債権に掛かる期限の利益を放棄できることに加えて、期限の利益が放棄されたもしくは喪失したことによって、弁済期が現実に到来していなくてはならない、というものでした。
消滅した債権を総裁のための自働債権とするには、それが消滅する前に受働債権と相殺適状になくてはならないとも。
Aは、過払金返還請求権を相殺のための自働債権として利用することで、借入金残金債務の支払をできるだけ小さくしようと考えたわけですが、最終的に相殺が認められることはありませんでした。
この判決が下される以前は、民法508条を引き合いに出せば、時効消滅債権であっても相殺に利用することができましたが、現在では厳しい判断が求められます。貸金業者を利用する人にとっては不利な判決であったといえるでしょう。

このコラムが気に入ったら
ぜひ「いいね!」をお願いします♪
みんなに役立つ情報をお届けします。